はじめに|面接の出来で「合否が決まる」時代
※ 面接の高得点合格の点数を285点から290点に修正いたしました(8/2)
医学部受験において、面接試験の重要性は年々増しています。
特に大分大学医学部の総合型選抜では、面接の配点が最大300点という高得点になっており、共通テストの得点だけでは合否が決まりません。
実際に、「面接の出来次第で逆転合格した生徒」もいれば、「筆記で有利でも、面接で評価されずに不合格となった生徒」も存在します。
「まだ面接の練習なんて早い」と思っていませんか?
多くの受験生が面接対策に本格的に取り組み始めるのは、高校3年の秋~冬頃です。
しかしその時期には、すでに志望理由書の提出期限が迫っていたり、共通テスト対策に追われていたりして、面接に十分な時間をかけられないケースがほとんどです。
その結果、せっかく出願したにもかかわらず、準備不足で自分の思いをうまく伝えられずに終わってしまう――そんな受験生も少なくありません。
面接対策は「早く始めた人」ほど、強くなる
面接は一夜漬けで身につくものではありません。
自分の考えを整理し、相手に伝える練習には時間がかかります。
だからこそ、本気で医学部を目指すなら、面接対策はできるだけ早く始めるべきなのです。
このブログでは、以下の疑問にお答えしていきます。
- 面接練習は、いつから始めるのが最適なのか?
- 最初はどんなことから始めればいいのか?
- 面接練習って、どんな内容で進められるのか?
- 実際に合格した生徒は、どう取り組んでいたのか?
面接が不安なあなたへ――。
早めの準備で、「自信を持って自分を伝えられる受験生」へと成長していきましょう。
【Q1】面接練習はいつから始めるべき?
「面接の練習って、出願が近くなってからでいいんじゃないの?」
そう考えている方は多いかもしれません。しかし、実際には面接の出来が合否を左右するからこそ、“いつ始めるか”が非常に重要です。
理想は「高2の秋〜高3の春」スタート
当塾でこれまで指導してきた中で、最も成長が見られるのは高2の秋〜高3の春にかけて練習を始めた生徒です。
この時期から準備を始めることで、
- 自己分析に十分な時間が取れる
- 志望理由書と面接内容の一貫性が作れる
- 複数回の練習で、緊張に強くなる
- 自分の強み・弱みを把握した上で仕上げられる
という多くのメリットがあります。
「夏以降」では遅い場合もある
実際、高3の夏以降に「そろそろ面接対策を」と来塾する生徒は多いのですが、
- 志望理由書の締切が近く、慌てて書き始める
- 一度の練習で上達すると思ってしまう
- 他の準備(共通テスト・願書など)と重なり、時間が取れない
というように、思うように対策が進まないケースが目立ちます。
「もっと早くからやっていれば…」と後悔する生徒は、毎年必ずいます。
早めに始めた生徒ほど、合格可能性は高まる!?
- 高2の冬から面接練習を始め、春には志望理由書のたたき台が完成
- 定期的に講師と対話を重ね、自分の考えを言葉にする練習を続けた
- 面接本番では、「面接官の目を見て、自信を持って話せました」と笑顔で報告
このような生徒は、面接の点数も高く、合格後も医療の現場で活躍できる素地ができています。
面接は“話す技術”ではなく、“自分を深く理解し、伝える力”です。
それを育てるには、時間と練習の積み重ねが欠かせません。
面接を重視する医学部だからこそ、「いつ始めるか」が合否を分けると言っても過言ではありません。
【Q2】最初の面接練習って何をするの?
「面接練習」と聞くと、いきなり模擬面接をするイメージを持つ方も多いですが、最初の段階でそれを行うのは実は逆効果になることもあります。
最初にやるべきなのは、自分自身を深く知ること=自己分析です。
ステップ① 自己分析|自分の価値観を言語化する
面接では、「なぜ医師を目指すのか」「なぜこの大学を選んだのか」など、深い問いが投げかけられます。
そのときに必要なのは、「他人に伝わる言葉で、自分の考えを語れること」です。
まずはこんな質問から始めます:
- 自分が感動したこと・悔しかったことは?
- 人からよく言われる自分の性格は?
- どんなときにやりがいを感じる?
- 医師という仕事にどんな印象を持っている?
書き出しやすいワークシートを使いながら、自分の軸を探っていくところからスタートします。
ステップ② 志望理由との整合性を整理する
面接で必ず問われるのが、「なぜ医学部なのか?」「なぜこの大学なのか?」という志望理由です。
この段階では、完璧な答えを作る必要はありません。
まずは、ざっくりとでも良いので考えてみましょう。
- 医師を目指したきっかけは?
- どんな医師になりたい?
- 大分大学を志望する理由は?(立地、教育方針、将来像との一致など)
この時点で書き出した内容が、後の志望理由書や面接回答の土台になります。
ステップ③ 質問に対する「話し方」の練習
ある程度、自己分析と志望理由が固まってきたら、実際に問われそうな質問に答える練習を始めます。
よくある質問の例:
- あなたの長所・短所を教えてください
- 最近気になった医療ニュースはありますか?
- 医師に必要な資質は何だと思いますか?
この段階では、答えの内容だけでなく、
- 声のトーン
- 話すスピード
- 話の構成(結論→理由→具体例)
といった点にも注意しながら、“伝わる話し方”の型を身につけていきます。
模擬面接は「準備ができてから」でOK
本格的な模擬面接は、これらの土台ができてから行うのが理想です。
焦らず、段階的に力をつけていくことが、面接本番での自信に繋がります。
最初からうまく話せなくて大丈夫。
大切なのは、「自分と向き合う時間を取ること」なのです。
【Q3】塾での面接指導はどう進めるのか?
面接は、ただ「質問に答える練習」だけでは身につきません。
本番で力を発揮できるようにするには、段階的なトレーニングと、一貫したサポート体制が必要です。
当塾では、受験生一人ひとりの個性や志望大学に合わせて、次のような流れで面接指導を行っています。
【STEP1】基礎編:一問一答で「自分を知る」
- 自己PR
- 長所・短所
- 医師を目指した理由
- なぜこの大学か?
こうした頻出質問に、自分の言葉で答えられるようにすることが最初のステップです。
最初はメモを見ながらでも構いません。
大切なのは、「自分が何を考えているのか」に気づくことです。
【STEP2】構成編:答えの「流れ」と「伝え方」を整える
答えの内容が整理できたら、今度は伝え方を練習していきます。
- 結論 → 理由 → 具体例 の順で話す
- キーワードを最初に提示する
- 相手の表情を見ながら話す練習
この段階では、講師が随時フィードバックを行い、「伝わる」話し方へとブラッシュアップしていきます。
【STEP3】実践編:模擬面接・集団討論・圧迫対応
最終段階では、実際の試験を想定した模擬面接に入ります。
- 志望大学の形式に合わせた質問練習
- 面接官役との1対1模擬
- 集団討論(大分大学医学部では毎年実施)
- 圧迫質問への対応トレーニング
場合によっては、講師が“意地悪な質問”を投げかけることで、あえて緊張感を高めた練習も行います
「この経験が、本番に活きた」と言ってくれた卒業生は少なくありません。
志望理由書の添削と連動した指導
当塾の面接指導では、志望理由書の添削と面接練習をセットで行うことを重視しています。
書いてあることと、話す内容にズレがあると面接官の印象が悪くなるからです。
毎回の練習で志望理由書を確認しながら、内容の深掘りと表現の調整を行うことで、一貫性のある受け答えができるようになります。
生徒に合わせたオーダーメイド指導
緊張しやすい子、話すのが苦手な子、自信が持てない子――
それぞれの課題に合わせて指導を調整するのが当塾の特徴です。
毎年、「最初は声も出せなかった生徒が、堂々と話せるようになった」という変化を数多く見てきました。
面接はトレーニングで伸びます。
そしてそれは、丁寧に寄り添ってくれる環境があってこそ実現できるのです。
【Q4】逆転合格した生徒の実例
「共通テストの得点が足りないかもしれない」
「面接が苦手で不安……」
そんな不安を抱える受験生にとって希望となるのが、“面接で逆転合格”した実例です。
実際に、当塾で指導した生徒の中にも、面接の出来が合否を大きく左右したケースがいくつもあります。
ケース①:共通テストがボーダーギリギリ → 面接高得点で合格
ある生徒は、共通テストの得点が地域枠の「足切りライン」をわずかに超える程度で、「正直厳しいかもしれない」と言われていました。
しかし、面接では300点中290点という高得点を獲得。
周囲の受験生が緊張でうまく答えられない中でも、堂々と自分の考えを語る姿勢が高く評価されました。
本人は「半年以上、面接練習を重ねてきたからこそ自信が持てた」と話してくれました。
ケース②:最初は声も出なかった → 毎週練習で“目つきが変わった”
別の生徒は、面接練習を始めた当初、緊張でうまく話せず、目線も定まらない状態でした。
最初のうちは、「何を話せばいいかわからない」「考えていることがまとまらない」と言っていた彼も、毎週の面接練習を通じて少しずつ変化していきました。
- 自分の考えをノートに書いて整理する
- 何度も同じ質問に答えて話し方を改善する
- 模擬面接で緊張感に慣れていく
その結果、面接本番では落ち着いて受け答えができ、見事合格を勝ち取りました。
指導していた講師が「目つきが変わった」と驚くほどの成長でした。
ケース③:圧迫質問をはね返す力をつけた
大分大学医学部では、面接で時に圧迫的な質問をされることがあります。
ある年、「本当にあなたは地域医療に貢献するつもりがあるのですか?」と、鋭く問い詰められた生徒がいました。
その生徒は、事前に圧迫練習を何度も重ねていたため、
「私は決して完璧ではありませんが、それでもこの地域で医師として成長し、貢献したいという気持ちは誰にも負けません」
と、落ち着いて自分の言葉で返答。面接官の表情がやわらいだ瞬間が印象的だったそうです。
逆転合格は、奇跡ではありません。
準備を重ねてきた人にだけ許されるチャンスなのです。
「面接は苦手だから……」とあきらめる前に、今日からできる準備を一つずつ積み上げていきましょう。
【Q5】面接が苦手な子に必要な「準備」と「環境」
「面接って、話がうまい人が有利なんでしょ?」
「緊張して声が出ない自分には無理かも……」
そう思っている受験生は少なくありません。
しかし、これまで多くの生徒を見てきた中で、「最初から面接が得意な子」はむしろ少数派です。
面接が苦手な子ほど「早く・小さく・継続的」に始めるべき
苦手意識があるなら、できるだけ早く、小さなステップから始めることが大切です。
- 最初は「話す」よりも「書き出す」ことからスタート
- 完璧に話せなくても、「考えていることを言葉にしてみる」練習
- 週に1回でも、人と話す機会を作るだけで変わってくる
「慣れ」と「安心感」が積み重なることで、次第に自分の言葉で話せるようになっていきます。
安心して話せる環境が、自信を育てる
面接対策で最も重要なのは、安心して自分を表現できる環境です。
- 否定されずに話を聞いてくれる大人がいる
- 繰り返し練習できる時間と空間がある
- 一人ひとりに合ったペースで進めてくれる指導者がいる
こうした環境があると、生徒は「話してもいいんだ」「間違えても大丈夫なんだ」と思えるようになり、自然と自信がついていきます。
「うまく話す」より「本音を伝える」ことが大切
医学部の面接官が見ているのは、「話術の巧みさ」ではありません。
むしろ、自分の言葉で本音を語っているかどうかが重視されます。
だからこそ、面接が苦手でも大丈夫。
自分と向き合い、時間をかけて準備すれば、必ず成長できます。
「緊張しやすい」「話すのが苦手」「何を言えばいいかわからない」
――そんな悩みを持っていた生徒ほど、半年後には見違えるようになっているものです。
大切なのは、「話せない自分」を責めるのではなく、「話せるようになるプロセス」に向き合うことです。
まとめ|面接対策は“早く・深く・本気で”
医学部入試において、面接試験の重要性はますます高まっています。
特に大分大学医学部のように面接の配点が300点もある大学では、面接の出来が合否に直結します。
だからこそ、「いつから、どのように準備するか」が非常に重要です。
面接対策で後悔しないために
- 「もっと早く始めておけばよかった」
- 「あのときしっかり話す練習をしていれば……」
- 「伝えたいことはあったのに、うまく言えなかった」
これは、面接で不合格になった生徒が口にする“後悔の声”です。
面接は、早く・深く・本気で取り組んだ人が、自信を持って本番に臨める試験です。
面接対策=自分自身を理解し、言葉にする力を鍛えること
面接練習は、「自分と向き合う時間」でもあります。
- 医師としての資質を問われる
- 自分の将来像を描く
- 人の話を聞き、自分の考えを伝える
これらは、受験のためだけでなく、将来医師として働く上でも欠かせない力です。
まずは一歩、始めてみませんか?
面接に不安があるのは、あなただけではありません。
だからこそ、「今」始めることに意味があります。
当塾では、面接対策に不安を感じている方のために、
- 志望理由書の添削
- 一問一答形式の練習
- 模擬面接(個別・集団・圧迫形式)
- 継続的なフィードバック
など、プロの家庭教師ならではの、一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
面接は、あなた自身を伝える場です。
自信を持って、自分の言葉で語れるように――。
その第一歩を、今ここから踏み出しましょう。
【面接対策の無料相談はこちら】

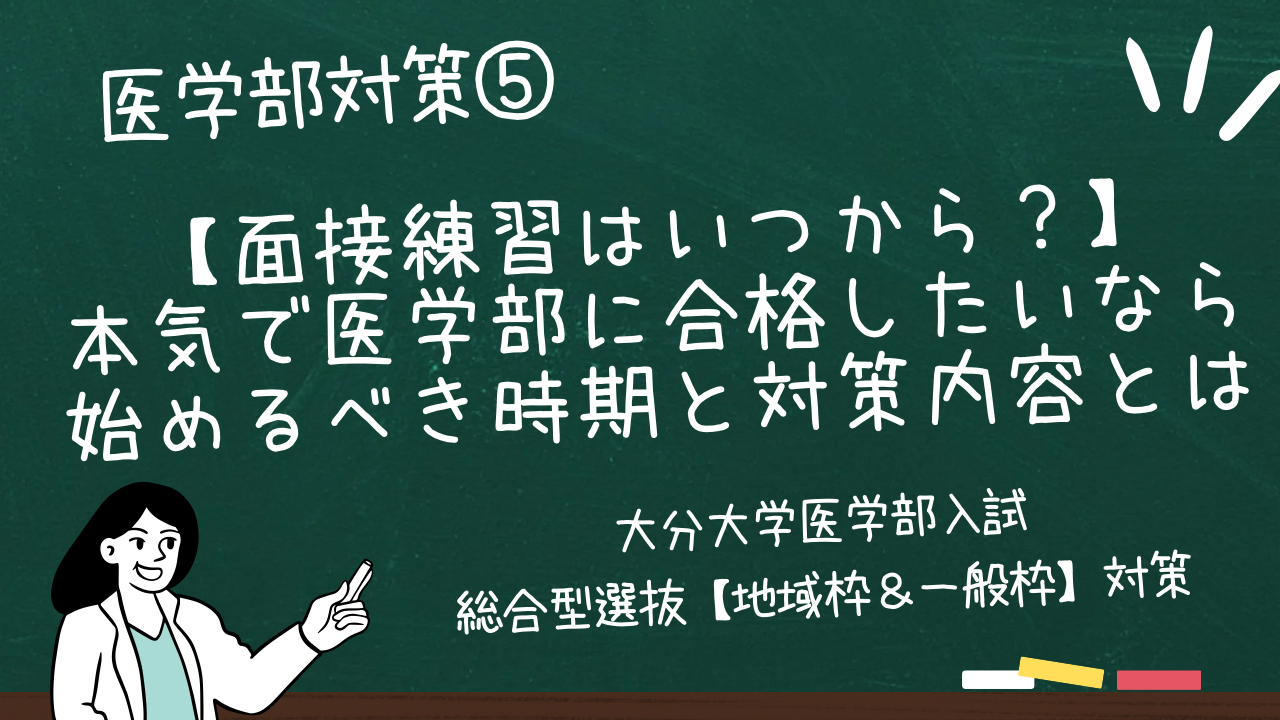
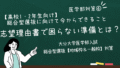
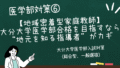
コメント