はじめに|総合型選抜は「3年生からでは遅い」理由
「大分大学医学部の総合型選抜に出願しよう」と思ったとき、多くの高校生が最初にぶつかる壁があります。
それが、「志望理由書に書けるネタがない」という現実です。
実際に当塾にも、高校3年生の夏以降になってから
「医学部に行きたいんですけど、何を書けばいいか分からない」
「何もしてこなかったので、書けることがありません」
という相談が毎年のように寄せられます。
大分大学の総合型選抜では、志望理由書や面接で以下のような項目が問われます。
医師になりたい理由(志)
大分大学を志望する理由(地域性)
リーダーシップや協調性、独創性に関する具体的なエピソード
これらに説得力を持たせるには、高校生活の中で何かしらの取り組みや行動をしてきた「事実」が必要です。
しかし、気づいたときにはすでに3年生の夏。
部活も引退し、学校行事も終わっている――そんな状態で「何もない」と焦ってしまうのは当然です。
だからこそ、総合型選抜は高校1年生・2年生のうちから準備しておくべき入試方式なのです。
高校生活の中での経験こそが、将来あなたの「武器」となり、志望理由書を支える“骨格”になります。
このブログでは、これから大分大学医学部の総合型選抜を目指す高校1・2年生に向けて、今からできること・やっておくべきことを丁寧にお伝えしていきます。
早めに知っておけば、それだけ有利になります。
「受験はまだ先」と思っている今こそ、動き始めるチャンスです。
【ポイント①】高校生活で「経験のネタ」をつくる
総合型選抜で最も重要になるのが、「自分の経験をどう語れるか」です。
大分大学医学部では、志望理由書において次のような視点が求められています。
- リーダーシップ(人をまとめた経験)
- 協調性(人と協力して何かを成し遂げた経験)
- 独創性(自分なりの視点や工夫)
この3つのキーワードに沿って、あなた自身の経験をエピソードとして語る必要があります。
ですが、高校3年生になってからこれらの経験を“つくる”のは、時間的にも精神的にも難しいものです。
だからこそ、高校1・2年生の今が最大のチャンスなのです。
「すごい実績」がなくても大丈夫
「部長じゃないとダメですか?」「コンクールで賞をとらないといけませんか?」とよく聞かれますが、そんなことはありません。
面接官が見ているのは「結果」ではなく、「取り組む姿勢」や「そこから何を学んだか」です。
例えば――
- 部活動の裏方としてチームを支えた経験
- クラスマッチで意見が対立したときにまとめ役になった経験
- ボランティア活動で地域の人と接した中で得た気づき
- 家庭での介護経験を通して感じた命の重み
どれも立派な“ネタ”になります。日常の中にこそ、語れる経験は眠っています。
医学部受験に活きる「習い事」や「趣味」もアリ
英語ディベート、絵画、書道、ピアノ、水泳、柔道、プログラミングなど、学校外での活動も、総合型選抜では評価対象になります。
重要なのは、「なぜそれを続けたのか」「それを通じて何を学んだか」を自分の言葉で語れるかどうかです。
実際、過去の合格者の中には、「小学生の頃から書道を続けてきた」という生徒が、その経験をもとに「集中力の大切さ」「継続することの意味」を語り、高評価を得ました。
今の行動が、未来の“志望理由書”を形づくる
高校生活での取り組みは、すべてが「志望理由書の材料」になります。
将来「自分はなぜ医師を目指したのか?」「なぜこの大学を選んだのか?」と問われたときに、胸を張って答えられるように、今この瞬間から“経験”を積んでいくことが重要です。
「目立つ役職がないから」「特別な活動をしていないから」とあきらめる必要はありません。
まずは身近なところから、一歩踏み出してみましょう。
【ポイント②】志望理由書の“タネ”を集めておく
総合型選抜において避けて通れないのが、「志望理由書」の作成です。
これは単なる“作文”ではなく、あなた自身の過去・現在・未来を通して、
- なぜ医師になりたいのか(動機)
- なぜ大分大学医学部を選んだのか(大学選択の理由)
- どんな医師になりたいのか(将来像)
を言語化し、説得力を持って伝える文書です。
しかし、この文章は突然書けるものではありません。
日々の経験、気づき、学びを“記録”しておくことが、完成度の高い志望理由書への第一歩なのです。
志望理由のタネは、日常の中に落ちている
例えば――
- 家族が病気をして病院に通った経験
- 学校で保健委員として活動した経験
- ニュースで医療問題に関心を持った瞬間
- 地域ボランティアで人と関わって感じたこと
これらはすべて、「医師になりたい理由」のタネになります。
その場では小さな出来事でも、後から振り返ったときに大きな意味を持つことがよくあります。
書き溜めておくことで、言葉が自分のものになる
おすすめなのが、「志望理由ノート」や「気づきメモ」を日常的につけておくことです。
- 医療ニュースを見たときにどう感じたか
- 自分が体験したことと、医学・福祉との関わり
- ボランティアや学校行事での気づきや反省
数行でも構いません。とにかく書き留めておくことが大切です。
それがやがて、あなた自身の言葉となり、志望理由書の“核”となります。
毎月1回、「自分の志望理由」を見直す習慣を
高1・高2のうちは、「なぜ医師になりたいのか」と聞かれても、うまく答えられないかもしれません。それで大丈夫です。
でも、考え続ける習慣があるかどうかは、後に大きな差となって表れます。
たとえば、月に1回「なぜ医学部を目指しているのか」を書き出してみてください。
- 最初は漠然としていてもOK
- 前に書いた内容と比べて、自分の考えの変化が見えてくる
- 回数を重ねるうちに、“本当に伝えたいこと”が見えてくる
こうした小さな積み重ねが、深みのある志望理由書と面接回答のベースになります。
総合型選抜の合格者に共通しているのは、「自分の言葉で語れる」こと。
それは、いきなり話せるようになるものではなく、積み上げてきた思考と記録の成果なのです。
【ポイント③】日常の中で「リーダー性」や「協調性」を育てる
大分大学医学部の総合型選抜では、「リーダーシップ」や「協調性」といった資質が、重要な評価項目として求められます。
しかし、ここで誤解されがちなのが、「リーダー=目立つポジションに立たなければならない」という思い込みです。
実際には――
- 部活動で副キャプテンとして支えた経験
- 委員会で人の意見をまとめた経験
- 友達のサポート役として裏方で動いた経験
このように表に出ない努力や、小さな気遣いも大切な「協調性」の証拠になります。
面接官は「役職の名前」ではなく「行動の中身」を見ている
面接で評価されるのは、肩書きではありません。
「どんな立場だったのか」よりも、「どんな行動をしたのか」「そのときにどう考えたのか」が重視されます。
たとえば――
- クラスで意見が割れたときに、どうやってまとめようとしたのか?
- 仲間と意見がぶつかったとき、相手の立場をどう理解したのか?
- 目立たない役割を自ら引き受けた理由は?
このような問いに、自分の経験をもとに答えられるようにしておくことが、志望理由書・面接両方で大きな武器になります。
「ふだんの過ごし方」そのものが評価対象になる
総合型選抜は、普段の学校生活そのものを見られる入試です。
部活の練習やクラスの掃除、行事の準備、友人との関わり――
どんな小さな場面でも、「人と関わる力」「自分で考えて動く力」が鍛えられます。
その日々の積み重ねが、面接や志望理由書で自然とにじみ出てくるのです。
失敗経験や悩んだことも「伝える力」になる
「うまくいかなかった」「悩んで途中でやめてしまった」という経験も、総合型選抜では“マイナス”にはなりません。
むしろ、そこから何を学び、どう次に活かそうとしたかが伝えられれば、人間的な成長が伝わる“プラス材料”になります。
受験生にとって大切なのは、完璧なエピソードを用意することではなく、等身大の自分の経験を丁寧に言葉にすることなのです。
【ポイント④】人の話を聞き、考える習慣を持つ
総合型選抜の面接や集団討論では、「話す力」だけでなく「聞く力」も問われます。
実際に医師という職業では、患者さんの話を正確に受け止めたり、チーム医療の現場で他職種と連携したりと、“聞く力”が極めて重要です。
だからこそ、大分大学医学部の面接でも、傾聴力や共感力、柔軟な思考が評価の対象となります。
日常会話の中で「聞く力」は鍛えられる
特別なトレーニングがなくても、日々の生活の中で“聞く力”を育てることは可能です。
たとえば――
- 友人や先生の話を、最後まで遮らずに聞く
- 会話の中で、「この人は何を伝えたいのか?」を意識する
- 聞いた話を、自分の言葉で要約してみる
こうした習慣を持つことで、自然と面接時の受け答えもクリアで論理的になっていきます。
ニュースや記事を見て「自分の意見」を持つ練習を
医学部の集団討論では、「医療の課題」や「社会問題」についての意見交換が行われることもあります。
その場で意見を出すには、普段から情報に触れて考える癖をつけておくことが大切です。
おすすめの習慣:
- 医療系のニュースや記事を週1回チェック
- 興味のあるテーマについて、自分の考えを100〜200字でまとめる
- 家族や友人と、その話題について軽く話してみる
これを繰り返すことで、「自分の意見を持ち、それを伝える力」が自然に育ちます。
要約する力=読解力・面接力・医師としての力にもつながる
情報を「要約する力」は、現代文や共通テストだけでなく、面接や医師としての説明能力にも直結します。
医療現場では、患者さんの話を要約して把握し、わかりやすく説明する力が必要です。
日常会話の中で、話のポイントを整理して伝える練習を積むことが、思考力・表現力のトレーニングになります。
日々の「聞く」「考える」「まとめる」という行動は、すべてが総合型選抜の準備になっています。
難しく考えすぎず、まずは今日から、周囲の人の話にしっかり耳を傾けてみてください。
【コラム】講師が見た「面接で輝いた生徒」の共通点
ここでは、実際に総合型選抜で合格を勝ち取った生徒たちの中から、「面接で輝いていた生徒」に共通する特徴をご紹介します。
結論から言えば、彼らに共通していたのは「自分の言葉で語る力」と「自分の経験を深く見つめる力」です。
小さな出来事を“深く掘り下げる力”
例えばある生徒は、クラスマッチで副リーダーとしてまとめ役を担った経験を語りました。
「ただの学校行事」と思われがちですが、その中で意見が対立したときにどう仲介したのか、チームで勝つためにどう動いたか――
その経験を丁寧に掘り下げて話すことで、協調性やリーダーシップを実感を持って伝えることができたのです。
「すごい活動をした」よりも、「ありふれた活動を深く語れる」ことの方が、実は面接で高く評価されます。
志望理由書を書きながら、自分を見つめ直していた
別の生徒は、志望理由書を夏から何度も書き直していました。
最初は「医師になりたい」とだけ書かれていた内容も、家庭の看護体験、ボランティアで出会った高齢者のこと、自分の弱さと向き合ったエピソードを通じて、少しずつ“自分らしい志望理由”に深まっていきました。
その結果、本番の面接でも自分の考えをブレずに語ることができ、評価されたのです。
表情や声のトーンにも「本気」がにじみ出ていた
そしてもう一つ印象的だったのが、「本気の人は表情が違う」ということ。
面接室に入ってくる目つき、話すときの声のトーン、志望理由書を机に出すときの所作――
言葉にできない部分に「この子は本当に医師になりたいんだ」という熱意がにじみ出ていました。
これは、一朝一夕でできるものではなく、日々の積み重ねが表情や姿勢に現れるものだと思います。
総合型選抜は、「その人の本質」が見られる入試です。
だからこそ、華やかな肩書きや実績よりも、「自分の人生とどう向き合ってきたか」「なぜ医師を目指すのか」がしっかり語れることが、何よりも大切なのです。
まとめ|高1・高2だからこそできること
大分大学医学部の総合型選抜は、「自分自身の経験や考え方を、自分の言葉で語れるか」が問われる入試です。
そのためには、高校3年生になってからの準備では間に合わないことがほとんどです。
部活動、学校行事、地域活動、家庭での出来事――
こうした日常のひとつひとつが、将来の志望理由書や面接で活きてきます。
高1・高2のうちからできることは、たくさんある
- 経験の“ネタ”をつくるために、小さなことでも挑戦してみる
- 志望理由書の“タネ”を集めるように、気づきをメモする習慣をつける
- 人と関わる中で、リーダー性・協調性を育てる
- 情報に触れ、自分の意見を持ち、聞く力・要約力を養う
これらはすべて、将来「医師として必要な力」であり、その力を持つ人を選ぶための試験が総合型選抜なのです。
「結果」よりも「どう考えたか・どう向き合ったか」が評価される
- 表彰歴がなくても大丈夫
- 特別な活動をしていなくても大丈夫
- 大切なのは、日々の経験をどう受け止め、どう言語化するか
今の時点で完璧である必要はありません。
でも、「考えること」「振り返ること」を始めているかどうかは、1年後・2年後に大きな差となります。
未来の自分のために、今日から一歩を踏み出そう
高校1・2年生でこの記事を読んでいるあなたは、すでに「準備を始めた一人」です。
当塾では、志望理由書の個別相談や、面接練習、将来を見据えたキャリア設計サポートも行っています。
少しでも不安がある方、自分の進路に迷いがある方は、ぜひ気軽にご相談ください。
医師になりたい。
その気持ちがあるなら、準備は「今」始めましょう。
【無料個別相談のお申し込みはこちら】

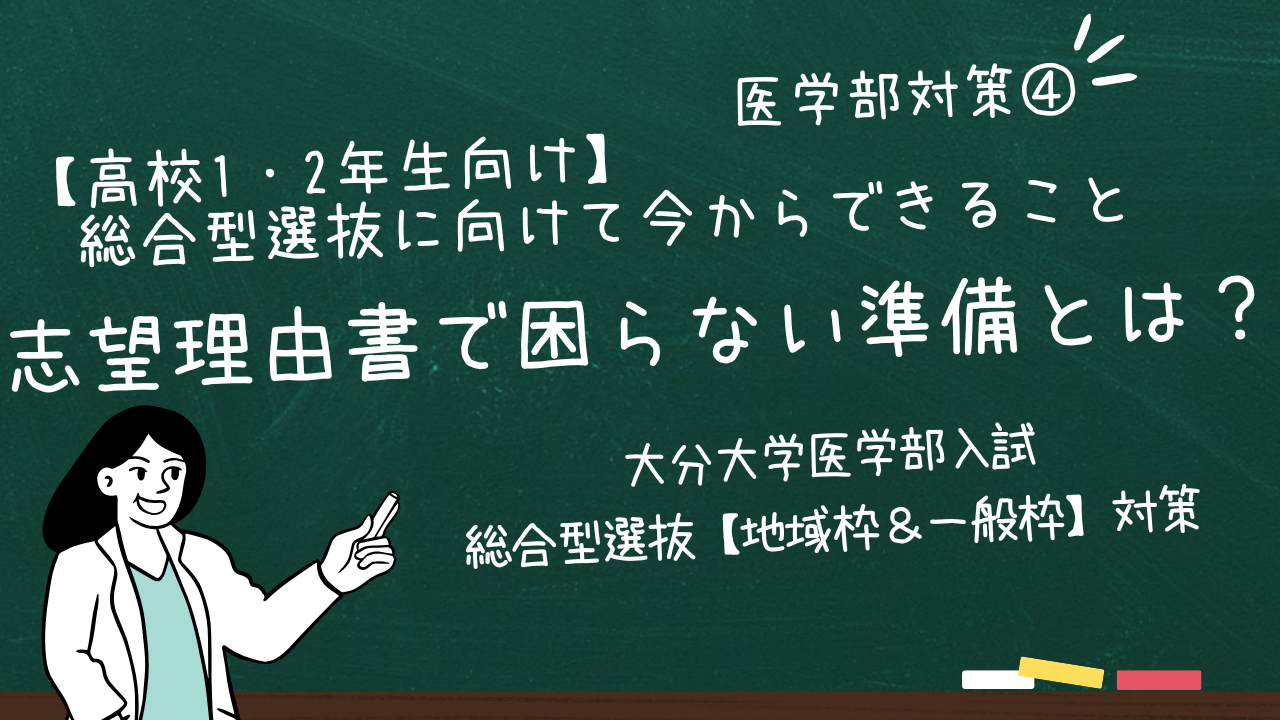
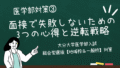
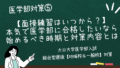
コメント